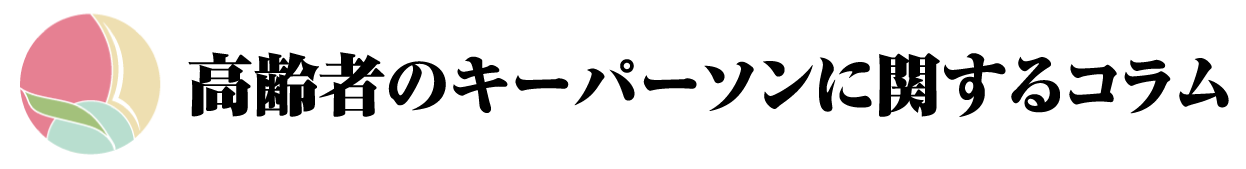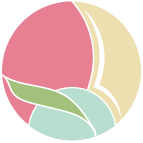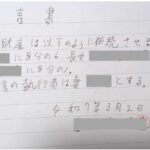認知症になると、財布の置き忘れが増えたり、ATMの暗証番号を忘れたり、お金に関し何かと不都合が生じ得ます。
予約していた美容院に行くのを忘れてしまったり、病院に行くのを忘れてしまうかもしれません。
老人ホームに入ろうにも、施設選びもままならず、家族がいれば家族が、家族がいなければケアマネジャーや自治体が、あなたの代わりに施設を選ぶことになるでしょう。
そうして、「こんなところに入りたくない!」、「家に帰りたい!」、「私のお金はどこ?!」といっても後の祭り、「認知症になってからの準備をせず、人のお世話になりながら、いまさら何を言っているんだろう」と、周囲の人は向き合ってくれないであろうからです。
帰ろうにも、自宅が、既に処分ないし賃貸なら解約されていることも少なくありません。「だったら自分で新しい所を契約する!」と言っても、能力も体力も落ち、八方ふさがりに陥るのが関の山でしょう。
「そんなの嫌だ!」と思う人は、迷わず、「任意後見契約」を結びましょう。この方法以外、認知症になってからの健康面、生活面、財産面を頼む制度は無いからです。
目 次 (クリックするとジャンプします)
1.任意後見の意味と趣旨
判断能力が不十分な人の代わりに、健康面、生活面、財産面の手続きや支払いを行う人を後見人と言います。
任意後見というのは、自分の意に任せて、誰を後見人にするか、何をいくらでやってもらうかを、認知症になる前に決めておく仕組みです。
任意後見で準備をする人は年間で1万人を超える程度ですが、その多くは、家族がいれば家族、家族がいなければ友人知人に、後見を頼んでいます。
任意後見をせず、誰に何をいくらで頼むかわからないほどの認知症になってしまうと、任意後見はもう頼めませんから「法定後見」という仕組みに乗ることになります。
法定後見はその名の通り法律で後見人、後見内容、後見費用を決めるということです。実際は、家庭裁判所の裁判官が、家庭裁判所に営業登録している弁護士や司法書士を後見人に選び、その人に、通帳、実印、保険証券、その他の全てを持って行かれます。
その後は、何にいくら使うかを決められ、およそ文句は言えなくなるのです。まさに、認知症なってからの準備、すなわち任意後見を事前にしておかなかったことに対する制裁と言えるでしょう。
以下、任意後見を頼む場合のポイントを伝授しますので、ご自分や気になる人に当てはめ考えてください。
2.任意後見の手続き
任意後見は公証人が認めて初めて成立する約束、すなわち契約です。
口頭でお願い&分かったよと言ってもだめ、書類に落としておく必要があります。
書類に落とすと言っても自分たちで紙に書いてもダメ、公正証書にしないと法律的な効果がないルールになっているからです。
公証役場は全国に300カ所弱あり公証人は500名程度います。どの役場でも、どの公証人にやってもらっても、費用(数万円の低い方)も効果も同じです。
公証役場で任意後見契約書を作成してもらうと、その内容の骨子が法務局に登記されます。不動産や会社が登記されるように、任意後見も社会に発信するために登記されることになっているからです。
任意後見を結婚に例えると、公証役場で作成し法務局に登記されている段階は婚約のステージと言えます。
数年から10年20年が経ち、頼んだ人の判断能力がだいぶ悪くなったら、家庭裁判所に後見スタートの手続きを取り、家庭裁判からGOサインが出たら、仕事を開始、すなわち成婚のイメージとなります。
このように任意後見は、公証役場での予約と家庭裁判所での本番、というように2段階あることを覚えてください。
3.誰に頼むか?
あなたは、認知症なってからの健康面、生活面、財産面の手続きやお金の受け渡しを誰に頼みますか?
後見人に資格は不要ですから、家族でもいいし、友達でもいいし、後見のことをやっているNPO法人や弁護士でも結構です。
相手が引き受けてくれないと任意後見は成立しないので、誰がいいか考え過ぎず、心あたりの人に、それとなく聞いてみる他ありません。
お金のことはAさん、健康面や生活面のことはBさんというように役割を分けて頼みたいならそれもOK。役割を分けずにAさんとBさんで一緒にやっていうのも制度上OKです。
頼める人がいないという方は、
- ・認知症にならないよう頑張って仮になったら法定後見を甘んじて受ける
- ・後見をやっているNPO法人や弁護士を探し、見比べ、気に入ったらお願いする(見比べ方がポイントになります)
のいずれかになるでしょう。
3.何を頼むか?
任意後見は代理契約ですので、自分の代わりに決めてやってもらう内容をラインナップ(列挙)することになります。
銀行とのやり取りはイメージが出やすいでしょう。保険に入っていればその手続き(契約内容の変更、満期が来た場合の請求と着金、場合によっては解約など)もお願いすることになります。
株をやっていれば、「このように運用してきたからその方針でやって欲しい」ということを具体的に書いておくことで、頼まれた人も迷うことなく管理運用できるようになります。
宝石や骨董品などはどうしますか?売って現金にするか、誰かにあげるからキチンと保管しておいてほしいか、希望と方法も任意後見契約書にキチンと書いておきましょう。
自宅はどうしましょう?最後まで自宅に居たいという人は、自宅は売らないよう明記しましょう。修繕をする場合は懇意の○○工務店に頼むとか、庭木の剪定はシルバー人材センターの○○さん(がいなくなってもシルバー人材センターがいい)と書いておくと明確になります。
別荘がある、収益物件としてアパートやマンションを持っている、田畑や山を持っている方もいます。それらをどうするかも決め、頼む人と話し合い、決まった内容書き込むことが肝要です。そうしておかないと、頼まれた人はどうしたらよいかわからず、安易に売るか放置するかのいずれかに傾いてしまうことが多いからです。
会社を経営している方も認知症になり得ます。会社をどうするか、持ち株(議決権)の及ぶ範囲で具体的な指示を記載しましょう。
健康面においては、手術をするかしないか、胃ろうや人工呼吸器を付けるか付けないか、かかりつけ医がいれば話して、いなければしかるべき人に相談し、自分の意思を固め、その旨も任意後見契約に落とし込みましょう。
介護サービスの内容も同じで、在宅がいいか施設がいいか、お風呂の温度は熱めがいいか温めがいいか、将来の自分を予測し文字に残しておきましょう。
認知症になったからといって、女性なら美容院やお化粧を放棄し、男性なら好きなゴルフや将棋を控え、お気に入りのジャケットを脱ぎ捨ててよいわけもありません。まだできているしやっているということで自尊心や自己肯定感も高まることが多いので、財産や健康面だけでなく、充実した生活を送るための手配や支払いもお願いしておきましょう。
なお、洗濯をして欲しい、オムツ交換をして欲しい、ということを盛り込むことはできませんが、それがきちんとなされているかを代わりにチェックして欲しいという内容は任意後見に当然に含まれていますので明記する必要ありません。
4.いくらで頼むか?
いくらで頼むか、相場があるようでない現状ですが、無料~月5万円をベースに、大きな仕事をした場合は都度10万円とか30万円と設定する場合が多いです。
この費用は、任意後見契約を結んだからといってすぐに発生するわけではありません。数年~20年を経て、いよいよ認知症による症状が重篤になり、「約束を果たすために一肌脱ぐか」ということで、家庭裁判所に手続きを取ってGOサインが出てから発生するので、実際に費用が発生する期間は3~5年ほどと考えておけば良いでしょう。
仮に、4年間、月3万円とすると、4年×36万円=144万円となります。
5.内容を変えたい場合
頼む内容や金額を変えたい場合、公証人に、「内容を変えたい」と連絡し、頼む人と頼まれた人で公証役場へ出向くか、頼んだ人がいる病院や施設に来てもらい、内容を変更します。
「あの人にはやはり頼みたくない」とか「あの人からの依頼は無しにしたい」と思う場合は、内容変更では収まりません。無しにしないといけなくなるからです。
無しにしたい場合、頼んだ人と頼まれた人で話し合ってからでもいいし、話し合わなくてもいいので、公証役場に連絡してください。希望を聞いた公証人が任意後見契約を解除してくれます。
家庭裁判所からGOサインが出た後の変更は、公証役場ではなく家庭裁判所に伝え、家庭裁判所がどうするかを決めることになっていますので、必ずしも希望通りになるとは限りません。つまり、任意後見が継続されるか、法定後見に切り替えられるかのいずれかになるでしょう。
なお、任意後見が始まったものの、本人の能力が回復したり、特に代わりにやってもらうことがなくなった場合、家庭裁判所にこれ以上後見は要らないという手続きを取ることで、完了することもあり得ます。
6.見張る人も決めておこう!
家庭裁判所からGOが出ると、後見人が契約書通りに仕事をしているかをチェックするためという理由で、任意後見監督人があてがわれることになっています。
誰が監督人になるかというと、家庭裁判所に営業登録している弁護士や司法書士がほとんどで、「この人は嫌だ」という文句は言えないルールになっています。
「後見人に無料でやってもらっているのに、監督人に月5万円取られておかしい」という人もあります。
そのようなこともあるので、やるのはAさん、見張るのはXさん、という風に、当初の契約段階で、後見人だけでなく、監督人(候補者)を明記しておくのも、自分らしい任意後見契約を作るポイントとなります。
現在の法律では、AさんとXさんが親族であってはいけないということになっているので、やるのは家族、見張るのは友達というパターンや、やるのはNPO法人、見張るのは家族という座組が良いかもしれません。
7.認知症になってからでも任意後見できますか?
認知症等になっても、「今後のお金、健康、生活面の手配や支払いをこの人に頼みたい」という気持ちや意識があり、それを、言葉や文字で伝えることができれば、OKを出す公証人は少なくありません。
ある公証人がダメでも、ほかの公証人はOkだった実例もあります。
認知症の診断を受けたからと言ってあきらめず、任意後見契約書の作成を試みるのはまさに身のため、見ず知らずの人が好き勝手にやる法定後見の道に踏み入っては絶対にいけません。