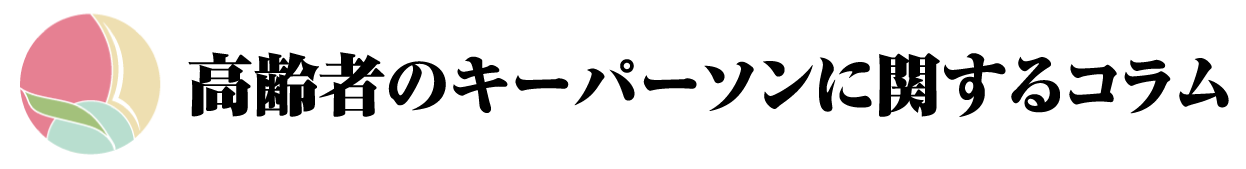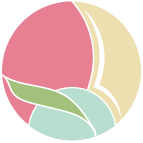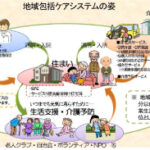どのような人が高齢者のキーパーソンになるのか、キーパーソンとして活動するための形態(法的根拠)、キーパーソンとして向き合う人・やり取りする相手、キーパーソンの権利と義務、について、説明します。
[この目次]
目 次 (クリックするとジャンプします)
1.どのような人がキーパーソンになるのか?
病院や施設から求められ、保証人や後見人のような「キーパーソン」になる方は少なくありません。その実態を見ていると、キーパーソンになる人は大きく4つの立場に分類できます。
最も多いのは、「ご家族様」というカテゴリーです。本人の家族ということで、キーパーソンになる場合です。
次に多いのは、「ご親戚様」という概念です。配偶者やお子さんがいない場合、本人の甥や姪などにあたる人がキーパーソンに就く場合です。
上記のような身内がいない場合、いわゆる「あかの他人」がキーパーソンになります。
まず、友人・知人が一肌脱いでキーパーソンになる場合があります。具体的には、昔からの友達、本人の様子を見る民生委員、ヘルパーやケアマネだった人がキーパーソンになる場合です。
知り合いではなく、病院や施設が紹介する、初対面の保証会社や弁護士・司法書士・社会福祉士などが、キーパーソンになる場合もあります。
しかし、見ず知らずの、しかも、キーパーソンを求める病院や施設が紹介する人に、自分の健康面やお金のことを託すことに抵抗を感じる人は少なくありません。
医療を受けないと命が危ないような場合、本人が居住する自治体が、「医療保護者」というキーパーソンになり、本人を病院に入れる場合もあります。
しかし、命に関わる、緊急性の高い医療ニーズが特段あるわけでなく、一人暮らしは危ないというだけで、医療保護という強い手段を利用し、長期にわたって、おひとりさま高齢者を精神病院等に入れてしまう場合も散見されます。
以上、誰が、どのような経緯でキーパーソンになるかによって、本人が、退院できるか否か、外出外泊できるか否か、身体拘束を受けるか否かなどが決まってくるので、「キーパーソン選び」には、慎重に慎重を重ねても重ねすぎることは無いと思います。
2.キーパーソンとして活動するための形態(法的根拠)
キーパーソンになると、いろいろな人とのやり取りが発生します。相手が、病院や施設ならまだよいのですが、銀行や保険会社などの金融機関になると、「キーパーソンであることの証明をしてください」と求めてくるでしょう。
このような場合、「親に頼まれた」とか「私、長男(長女)です」と言っても相手にされません。
ということで、キーパーソンであることを相手方に証明する方法に関し、4つの形態(法的根拠)の概要をご紹介します。
ア. 本人から頼まれ引き受ける「委任契約」
本人から頼まれた内容がつづられている契約書です。例えば、「通帳や印鑑を預かって欲しい。必要に応じそれを銀行へ持って行きお金を下ろし病院からの請求書に応じて支払いをして欲しい。」という内容を契約書に落とし込んでおく財産管理委任契約があります。このような契約書を持って行くことで銀行は、「そのような依頼を受けているのですね」ということでスムーズに対応してくれるというわけです。
イ. 本人の取引先から頼まれ引き受ける「保証人契約」
保証人契約は特殊です。というのも、当の本人とではなく、本人の取引先である病院や施設とキーパーソンが結ぶ契約だからです。
保証人契約の内容は、お金と掃除といえるでしょう。入院している本人が費用を払わない場合、代わりに自腹を切りますというお金の面と、本人が亡くなった場合、入れ歯などの私物の撤去や、遺体の引き取りについて葬儀社と事前あるいは遅滞なく連絡を取り、次の患者さんのためにベッドを使えるよう原状回復する役割ということです。
ウ. 裁判所から選ばれ引き受ける「法定代理人」
認知症等が重くなると、自分で、誰かに、何かを頼むことができなくなります。そのような場合、自治体等が家庭裁判所に、「この人に代理人(キーパーソン)を付けてください」という手続きを取ります。すると、裁判所は、裁判所に営業登録している弁護士・司法書士・社会福祉士などから1名あるいは2名に声をかけ、また、声がかかった人が引き受けることで、その人が本人の後見人(という名の代理人、すなわち、キーパーソン)になります。
エ. 自治体による「措置」
本人が居住している自治体が、公権力(措置権)を発動し、高齢者等の意向に関係なく、本人を施設等に入れる場合もあります。
行政による措置は強い権力ですから、一度、病院や施設に入ると措置が解除されない限り退院退所することができなくなります。
3.キーパーソンとして向き合う人・やり取りする相手
キーパーソンになると、主役である本人、主な取引先である病院ほか、本人の親戚、自治体・公証人・警察、などと向き合うことになります。
キーパーソンにとっての主役は何といっても、「本人」です。対象が身内の場合だったり他人の場合もありますが、年齢は、およそ70代から90代が多いでしょう。本人の健康に留意しながら、本人の財産を上手に活用し、本人の人間関係を良好に保ちながら、長年培って形成された本人の価値観を大切に、有意義な生活を送って頂くサポートをすることになります。
キーパーソンの「取引先」は、病院、施設、銀行、保険会社、自治体、お寺、等になるでしょう。病院の場合は、医師・看護師・相談員などと、胃ろうをつけるかなど、込み入った内容について話を詰めていくことになります。保険会社に対し、保険金の請求や受け取りの手続きをすることになります。
「本人の親戚」とのやり取りもあり得ます。相続権のある親戚もいれば、相続権のない親戚もいらっしゃるでしょう。本人の近所の方や古くからの友人などとも、本人について連絡を取り合うことがあるかもしれません。
その他、任意後見契約や公正証書遺言を作るときには公証人と、成年後見制度や遺産分割協議を行う場合は家庭裁判所と、迷子になったりすれば警察と、のやり取りも発生します。
4.キーパーソンの権利と義務
キーパーソンは、3つの権利をもちます。それぞれ、代理権、同意権・取消権、報酬請求権です。
「代理権」とは、本人に代わって、老人ホームと契約を締結したり、保険会社に保険金を請求するときに使う権利です。
「同意権」は、本人がすることを良しとする場合に使う権利です。例えば、本人が携帯電話の契約をする場合、その契約内容でよければ、キーパーソンとして携帯電話の会社に同意することで、本人と携帯電話会社の契約が成立します。
逆に、本人がした契約が、本人にとって不利不当だと思えば、「本人がした契約を取り消します」と伝えることで、携帯電話の契約を無しにすることができます。これを、「取消権」と言います。
「報酬請求権」は、委任契約で定めたキーパーソンとしての報酬(例えば月3万円)を、本人に請求して受け取る権利です。
キーパーソンには3つの義務が課されます。身内以外の方のキーパーソンになる方は、特にしっかりと理解し、キーパーソン活動に勤しんでください。
まずは、「善管注意義務」です。善良なる管理者として、本人の健康や財産をきちんと見張り、管理する義務のことです。放っておいたり、失くしてしまうようなことがあってはいけません。
「報告義務」は、キーパーソンの活動や業務を管理する人に対し、キーパーソンとして何を、どのようにやった、ということを報告する義務です。委任契約であれば依頼された本人に、後見人であれば家庭裁判所に、という具合に報告する対象が変わるので気を付けましょう。
「身上配慮義務」は、本人の気持ち、生活、健康状態、経済状況を踏まえ、本人のために、代理権、同意権、取消権を行使しなければいけないという義務です。要するに、キーパーソンの思い込みや都合で仕事をしてはいけませんということです。