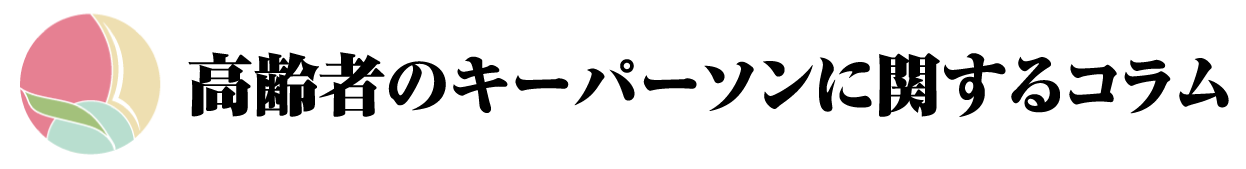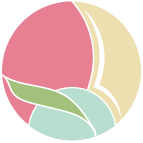高齢者のキーパーソンの悲喜こもごもを、実際の作文レポートから抜粋する形で紹介します。
家族として、介護職として、本人に面し、その時、何を考え、何をし、あるはせず、今、何を思っているのか。また、主役である高齢者自身の状態や身上はどうだったのだろうか。何が促進要因で、何が後退要因なのか。
1~6までのシーンを想起しながら、じっくりと感じ考えてみて下さい。
また、空欄になっている「 」に自分なりのタイトルを付けてみましょう。さらに、理解が深まるはずです。文字数は問いません。
1「 」
認知症が進み、要介護3になったので、兄弟姉妹で相談し、東日本大震災の後だったこともあり、「耐震補強工事をするから工事が終わるまでここでお泊りしていてね」と母をグループホームに入所させました。
その後、訪問するたびに、「迎えに来てくれたの?」と言われ、「まだ工事しているのでもう少し待ってね」と言って帰る時、後ろ髪を引かれる思いだった。
夫・妹・弟夫婦・孫たち・おばも時々訪問していましたが、そのうち母親は口数が少なくなりました。
要介護5になり、申し込んでいた特別養護老人ホームに入ることができました。その後、食事量が減少、老衰で、85歳で亡くなった。
グループホームの費用は父の遺族年金では少し足りず私と弟が毎月フォローしていたが、特養に入ってからは費用が安くなり年金で賄うことができ、少し貯金することができた。
今思うと、その時は、最善の判断で自己満足していたように感じるが、認知症だったとはいえ、母の気持ちをまったく考えずに無視していた様で、今でも胸が苦しくなります。
2「 」
「こんな歳を取ってまで、なんで学校みたいに朝早くから出かけなくてはならないの?」と昭和9年生まれの母に言われたとき、ケアマネジャーから促されるままにサービスをスタートしたことに反省、サービスを止める決断をしました。
母は、60代で半月板損傷を患い手術を受けましたが、完治しなかった足の痛みがありました。そのため、80歳を超えた母にとっての通所は、大きな負担だったと思います。
以来、母の意思を尊重し、在宅で寿命を全うさせることに重きを置くようにしました。
しかし、私一人での介護には知識や情報が不足しており、すべてが後手に回る状況でした。
昼間に私が仕事で家を空ける際、テレビを24時間付けていましたが、その結果、母がベッドで眠る時間が増え、脚の筋肉が固まってしまいました。これにより、体位を換えると痛がるようになり、オムツ替えが困難になり、足のかかとに褥瘡ができてしまいました。
褥瘡の治療に9か月を要しましたが、これを機に、訪問医療、訪問看護、リハビリテーション、訪問介護のケア体制を整えることができました。
医療においてはドラッグロック(薬による制限)、看護においては身体拘束の提案もありましたが、医療や看護の時間帯に私が在宅することで回避しました。
振返ると10年、ケアマネジャーやケアスタッフの支えがあり、私は多くの活力を頂きました。母も、アルツハイマー病を抱えながらも、軽食を摂りながら穏やかな生活を送り、最期の昏睡状態に陥る前まで意思表示ができました。
3「 」
私が経営するデイサービスが大好きで、ほとんど毎日のように来所されていた80歳の女性についてです。
デイサービスでは、ご自分の認知症を自覚され、涙ぐむことも多かったです。
ある時、自宅の火の始末について、ご近所から苦情が出て、区役所に相談があったようです。担当者会議が開かれ、私としては、これまでも日常生活に大した支障はなかったこと、歩行や挨拶もしっかりしていたことなどから、要介護度はそれほど大きくならないのではないかと発言しましたが、聞き入れられませんでした。本人の意思も無視され介護度は3となり、施設に送り込まれてしまいました。
「大好きだったデイサービスのご利用も可能にしてくのでアパートを引きあげるのは待って欲しい」と娘さんたちに伝えましたが、叶いませんでした。
後日、施設に面会に伺った際、「私をここから出して!」、「通帳を渡すから、お金を引き出してきて欲しい」と言われました。私の手を握りしめて訴えていた表情が気になりました。
娘さんに会いに行きましたが会って頂けず、その後、まもなく、ご本人はお亡くなりになりました。
4「 」
包括のケアマネとして担当した91歳、男性、生活保護受給者のことです。
足のどこかに痛みがあるようで、歩行状態が悪化しつつあった。受診をまったくしておらず、疾患等の情報が無かった。
入浴はしていない。エアコンはなく、夏は扇風機、冬は小さい電機のストーブのみで生活していた。冷蔵庫はあるが古くて使っていない。
電気の支払いを忘れて電気が止まることが時々あった。大家さんが止めたと思い込み、大家さん宅へ文句を言いに行くこともしばしばだったが、包括が訪問する時にはスリッパを出してくれるなどの配慮はあった。
食事はバスに乗って繁華街のレストランへ行って食べるので、直ぐにお金が無くなることを繰り返していた。1か月の使用できる金額を考えずに使っていたので、一緒に生活費の使用配分を考えて紙に書いて渡したりしていたが、本人はその通りにするつもりが全く無かった。
担当だった私が異動になり、後任に引き継いだが、支援は継続されず、本人は自宅で孤独死の状態で発見されるという始末になった。
本人としては自由気ままに生きていた様子ではあったので、それで良かったのかもしれないが、もっと何かできる事があったのではないかという気持ちが残っている。
5「 」
父が亡くなり、母が姉家族と同居するようになりました。面倒見の良い姉は、義理の父の介護を5年ほどやって看取った経験がありました。
1年半ほどたったある日姉から、「母から泥棒扱いを受けた」ほか愚痴の電話がありました。その後も、「何もしてくれないと怒鳴られた」などの電話が頻繁に来るようになりました。
私は母を施設へ入れるよう勧めましたが、「母のためには私が面倒を見るのが一番」、「母も施設には行きたがらない」と言い張ります。やさしかった昔の母を自分のちからで取り戻したかったのかもしれません。
1年くらいかかって何とか姉も同意してくれました。施設に入ってからの母は、言動も以前の母に戻り、顔つきも変わっていったことをよく覚えています。姉も母の変化には大変驚いていました。
施設へ入って3年くらいたったある日、母が高熱で入院したとの知らせがあり急いで病院へ行くと、発熱は誤嚥性肺炎によるもので、ICUで治療中とのことで面会できませんでしたが、以前にも同じようなことがあったので、大事には至らないだろうと楽観しておりました。
一週間ほどしてICUから出てきた母に面会すると、少しぐったりしたようではありましたが、母と姉と私での久しぶりの会話を楽しんだものでした。
担当医から話があると言うので伺うと、「食欲が戻ってこない、このままだと『おみとり』か『延命』のどちらかになります」と唐突に伝えられました。
また、コロナ禍が癒えていない頃で、『おみとり』の場合は毎日面会に来ても良いが、胃ろうをして『延命』する場合は面会できないとも言われました。担当医の言葉は母を死へ追いやるためのものに思いました。
入院する数週間前の七夕には、施設で楽しそうに短冊をつるす母の写真がメールで送られて来たりしていたのですから、私としては本当に唐突の宣告で、直ぐに決断できるはずなどありません。
姉に判断を一任された私は、二週間ほどしてからも食事の戻らない母に対し、『おみとり』を選択しました。あきらめきれず姉と共謀し、母の口へ食事を押し込んだりもしてみましたが、それから二週間余りで天国へ逝くことになりました。入院から1か月と7日目のことでした。
毎日面会に行けたことがせめてもの救いですが、この選択への疑念や無念さは今も消えることはありません。
「どうしたらいいの」、「こわいよ―」という母の言葉とともに、あの時の記憶が今も蘇ってきます。
6「 」
逝去一か月前、自宅で突然嘔吐し入院となる。精査後診断は、“すい臓がん末期、余命1か月”とのこと。
仕事の都合がつかず、2週間後に病院に見舞う。思った以上に元気で顔色も良く空くし安心する。「もう3日ごはん食べていない」という母、「おなかすいた?」と聞くと、「すいてはない」と笑顔、「もう歳だからおなかも空かない」ともいう。
「家に帰りたい、仏壇が気になる、花も枯れてるんじゃないかな」と母、「先生に聞いてみようか」というと、「だめって言われると思うよ」と応える。
幸い姉が看護師で、「家でも点滴ができる環境であれば許可できる」とのことで、二泊三日で帰宅することができました。
自宅へ帰ると母の友達が3日続けて顔を見せてくれ母もとても嬉しそうでした。家では、痛むも苦しみも全くなく、普通に穏やかに過ごしました。
その後、病院に戻り、1週間後に亡くなりました。
これで良かったのか、もっとできることがあるのでは等、色々思ったことはありますが、何一つ話し合って決めたことがない家族でした。その時は、せめて家に帰りたいという思いを深く考えることなく、何となく実行できたに過ぎない程度のことでした。
ただ、これから思うことは、相手が話しやすい環境を作り、聞いたり、小さなことでも一つ一つ叶える、満足ということではないですが、楽しかったと思って頂ける努力をしたいと思います。