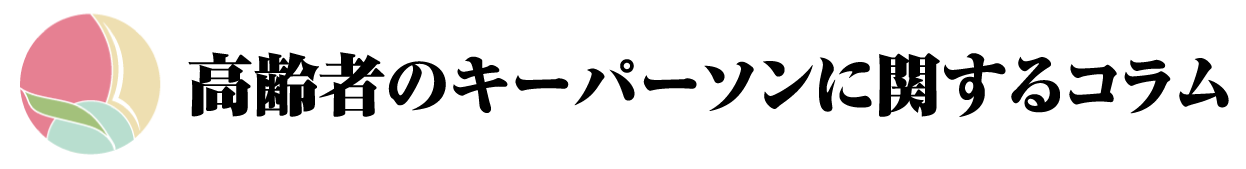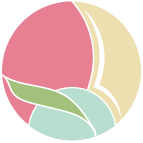加齢とともに、見づらい、聞こえづらい、外出したくないなど、何かと億劫になり、庭掃除、ペットの散歩、雪下ろしなどを、誰かに頼まざるを得なくなることが増えてきます。
このような、身の回りや家の周りのお世話をお願いするのが「お世話契約」です。
加齢とともに、銀行・保険会社・証券会社とのやり取り、自宅・アパート等の収益物件・田畑山の管理・売却、老人ホームや病院との契約や費用の支払いがままならなくなることがあります。
このように、自分の財産に関する事務面を頼む場合に結ぶのを「財産管理委任契約」と言います。
お世話契約や財産管理委任契約に関するセミナーをすると、「そんな契約、結ばなくても大丈夫、みんな助けてくれているから」という人がいます。
しかし、それは甘いか無責任な考えと言えるでしょう。
なぜなら、「どのような立場でそのようなことをしているのですか?」と聞かれたら、あなたのために頑張っている人は、「家族だから、ご近所だから、ちょっと頼まれて」と言うにとどまります。すると、「そうですか、ご本人から正式に頼まれているわけではないのですね、であればお引き取りください」とけんもほろろに相手にされないからです。
そして、「これ以上関われない、ごめんなさい」とあなたとその方の縁も切れてしまうことがしばしばだからです。
ということで、「親しき仲にも礼儀あり」、きちんと、書面で契約し、助ける・助けられるというお互いさまの関係を、いざという時、第三者に提示できるよう形にすることは大切かつ必要なことなのです。
以下、お世話契約と財産管理委任契約の例を紹介します。自分や気になるあの人の場合、どのような内容になるか、具体的に考え、独自のお世話契約や財産管理委任契約を作成することをお勧めします。
目 次 (クリックするとジャンプします)
1.お世話契約の事例A:叔母と姪
高齢で施設暮らしの叔母に頼まれ、身の回りの世話やお金の管理をしてきた姪が、叔母との間で結んだものです。
叔母は足腰が衰え1人での外出がままなりません。
姪は、自分が世話をするしかないという思いだけで長年世話を引き受けてきましたが、ふと、「ほかの親戚から見たらどう思われるのだろう」という不安がよぎりました。というのも、叔母の自宅がある自治体から、「(叔母の)空き家をどうする予定ですか?」という照会が来たことがあったからです。この先、入院などが発生した場合など、姪という立場だけでは乗り切れないのではないかと考えたからです。
これまでしてきたことを振り返り、先々のことを想定し、契約を結ぶことについて、勇気を振り絞っておばさんに伝えると、「私もそう思っていたところ、あなたがそこまで考えてくれていて嬉しいわ」と、二人の関係はなお良好になりました。
このケースでは13の依頼内容がまとめられました。同居家族なら自然にすることばかりですが、別居している親戚ですし、このように文字に落とすことが重要です。
~叔母と姪で結んだ約束事リスト~
- ① 通院、通所の同行介助をすること
- ② 日用品の購入をすること
- ③ 定期的に美容院を予約し同行すること
- ④ 要介護支援更新認定の申請ほか必要な行政手続きを代わって行うこと
- ⑤ 医療や福祉事業所を利用する場合に身元引受人となり、入退院及び入退所に必要な手続きをすること
- ⑥ 入院や福祉事業所を利用する場合に連絡窓口となること
- ⑦ 入院・入所をした場合、定期的に面会し、本人の状態を把握すること
- ⑧ ケア会議に出席し、ケアプランに同意し、同意書に署名すること
- ⑨ 病院や福祉事業所の要請に応じて各種ワクチン接種に同意し、同意書に署名すること
- ⑩ 本人名義の通帳を預かり必要時に入出金・送金等を代わって行うこと
- ⑪ 入院・入所をしたために自宅が空家状態になった場合に、屋内清掃・換気・敷地の清掃など不動産保全のための管理をすること
- ⑫ 郵便物を開封し内容を確認し必要な手続きを代わって行うこと
- ⑬ 上記に関連するすべてのこと
「あれも頼みたい」ということが発生したら、このリストに都度追加すれば大丈夫です。
費用ですが、姪をねぎらう意味で、叔母は月4万円のお世話代を払うことにしました。それに従い、これまでの2年ほどの業務を清算し、叔母が亡くなるまで、姪御さんはお世話をする決意を新たにすることができました。
2.お世話契約事例B:叔母と姪&甥
自宅に一人で暮らす叔母が、近くに住む姪、および、車で1時間ほどの所に住む甥、に以下のことを頼んだケースです。
~叔母と姪&甥で結んだ約束事リスト~
- ① 排泄の介助をすること
- ② 洗面・入浴・着替えなど身なりを整えることの介助
- ③ 食事の提供と後片付けをすること
- ④ 食事の介助をすること
- ⑤ 服薬の管理をすること
- ⑥ 部屋の掃除をすること
- ⑦ 衣類や寝具の洗濯と整頓をすること
- ⑧ 医療や福祉サービスを利用する場合に身元引受人および保証人となり、必要な契約などをすること
- ⑨ 病院への通院、施設等への通所の介助をすること
- ⑩ 手持ち現金の管理をすること
- ⑪ 郵便物を開封して内容を確認し、必要な手続きなどをすること
- ⑫ 以上に関連するすべてのこと
先のケースAに比べると、①~⑦にあるように、排泄の介助、洗面・入浴・着替えなど身なりを整えることの介助、食事の提供と後片付け、食事の介助、服薬の管理、部屋の掃除、衣類や寝具の洗濯と整頓、など介護や家事支援の内容が含まれています。
甥と姪で役割分担をして、①~⑫の仕事をすることになっていますが、やはりメインは、近くに住む姪となるので、謝金は、姪が月3万円、甥は月2万円となっています。
もちろん、姪が全ての介護を行うわけではなく、介護保険制度のサービスをフルに使ったうえで、補完的に介護等を行うことになっています。
3.お世話契約の様式
お世話契約の全体像は、およそ以下の通りです。
冒頭に、下記のような趣旨を書きます。
次に、以下のような目的を書きます。
以降、いつからいつまでの約束なのか(期間)、何を頼み頼まれるのか(内容:上記に掲載した約束事のイメージ)、いくらでお願いし引き受けるのか(報酬)、頼まれた人の義務、契約を解除したい場合のこと、契約が終わる時の条件などを書きます。
そして、契約書の最後に、
とし、契約の日付と、頼む人と引き受ける人の氏名と住所を書き、印鑑(実印でなくても大丈夫)を押します。
他人ならまだしも、身内でもこんなことまでしなければならないのかと思うかもしれません。しかし、身内だからといって曖昧にすると、何をどこまで、いつまでやらなければいけないのか不明ですし、お世話が長期化すると、なぜ自分ばかりがしなければならないのか、自分の生活もあると疲弊しかねません。このように、契約することは、お世話をしてくれた人をも守ることにもなるのです。
なお、謝金は無償でも構いませんが、ある程度の金額を取り決めた方が、お互いにスッキリすることが多いように見受けられます。
4.財産管理委任契約の骨子
財産管理委任契約は、頭を使って財産をどうするか代わりに決めてもらう代理人契約と言えます。
家族だから当然に代理人になれると思ったら大間違いです。代理権は頼む本人(委任者)から与えられなければ生じないからです。
ということで、財産管理委任契約のポイントは、代理権を与え「代理人」とすることであり、代理してもらう内容を「代理権目録」として文字にしておくことになります。
5.財産管理委任契約の例:高齢男性と支援するNPO法人
奥様に先立たれ、息子2名と疎遠かつ険悪な高齢男性と、その男性を支援するNPO法人の間で結ばれた財産管理委任契約の実例です。
男性がNPO法人に託した代理内容、すなわち代理権目録は次の通りでした。
~代理権目録~
- ① 預貯金通帳、有価証券、社会保険関係等重要な財産及び重要な書類の管理をすること
- ② 以下の金融機関を含むすべての金融機関への預入れ、引出し、新規契約、解約、送金手続、代理人届、その他一切の手続をすること
- ・●●銀行 ●●支店 普通預金 口座番号
- ・●●銀行 ●●支店 普通預金 口座番号
- ③ 以下の保険会社を含むすべての保険会社との新規契約、契約の変更、更新、解約、請求、受領、その他一切の手続をすること
- ・●●生命 終身保険 証券番号
- ④ 住居及び住環境の整備と修繕の手配及びそれらにかかる費用の支払いをすること
- ⑤ 年金等定期的な収入の受取り、給付金等の請求及び受領、光熱費等生活にかかる費用の支払いをすること
- ⑥ 生活用品の購入、外出時の交通費、外食費その他介助に必要な費用の支払いをすること
- ⑦ 医療機関の入退院手続き及び医療費の支払いをすること
- ⑧ 介護サービス並びに有料老人ホーム等福祉施設の利用契約の締結、変更、更新、解除をすること
- ⑨ 委任事務の遂行に必要な郵便物の受領、開封及び閲覧をすること
- ⑩ 依頼者が、訪問販売等で不利な契約をした場合に、相手方に対し契約解除、取消し等の意思表示をすること
- ⑪ 登記及び供託の申請、税金の申告・納付、行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払い、不服申立てをすること
- ⑫ 住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明書その他行政機関が発行する証明書の申請と受領をすること
内容を見ると、硬い言葉が並んでいますが、要するに、契約に関することや契約に伴う金銭の授受などを代わりに頼む、ということです。
6.財産管理委任契約書の様式など
お世話契約と同様、財産管理委任契約書においても、どうしてこのような契約を結んだかという契約の趣旨、頼む内容の明記、代理人の仕事をするために必要な通帳等の引渡し、代理人報酬額の定め、依頼者に対する業務報告の頻度や方法、契約内容を変更する場合の方法、契約を解除する場合の方法、契約解除となった場合は預かっていたものを依頼者に返却する定め、どちらが亡くなった契約は終了するなどの契約終了の条件、などを明記します。
代理人として取引をするときは、銀行や施設等の相手方に財産管理委任契約書を提示し、「私は代理人の○○です」「このように本人から代理権を与えられています」と立場を表明します。
しかし、相手方が代理人との取引に応じるかは相手方次第です。多くの場合、本人に電話で確認したり、本人を連れてきてくださいと言われることもあります。
このことは、公正証書であっても私文書であっても同じで、多少面倒ですが、財産管理委任契約が無ければおそらくまったく相手にされないことを考えると、財産管理委任契約書を作るに越したことはないでしょう。
なお、お世話契約にしても財産管理委任契約にしても、頼んだ人がきちんとやってくれているか心配になることもあるでしょう。そのような時は、するのはAさん、見張るのはXさんという具合に、チェックする人も当初の契約の中に盛り込んでおくのが賢明です。